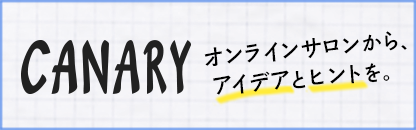特集「挑戦前夜」
卒業や就職を迎えるこの季節。新たな「挑戦」をしてみたいと考えている人も多いはずです。
この特集では、様々なジャンルのトップランナーに、その後進んでいく道を決定づけることになったきっかけ・決心について伺い、各人の挑戦前夜の様子を描き出します。
ソロユニット「Sunaga t experience」としての活動筆頭に、ヨーロッパ、アジア等海外公演も行うジャズDJ界の巨匠・須永辰緒。 自身でセレクトしたジャズ・コンピレーションアルバム「須永辰緒の夜ジャズ」シリーズが人気を博すなど、レコードを掘り続ける姿勢とその情熱から「レコード番長」の異名を持つこの男。DJという職業が一般的ではない時代に、DJとして生きていこうと決意したきっかけはなんであったのか。前人未到の地に足を踏み入れクラブシーンを切り開いた、波乱万丈の人生。須永辰緒の挑戦に迫る。

須永辰緒(Sunaga t experience)
Sunaga t experience =須永辰緒によるソロ・ユニット含むDJ/プロデューサー。 DJプレイでは国内47都道府県を全て踏破。また北欧=日本の音楽交流に尽力、世界各国での海外公演多数。 MIX CDシリーズ「World Standard」は12作を数え、ライフ・ワークとも言うべきジャズ・コンピレーションアルバム 「須永辰緒の夜ジャズ」は20作以上を継続中。国内や海外レーベルのコンパイルCDも多数制作。国内外の多数のリミックスワークに加え自身のソロ・ユニット”Sunaga t experience”としてアルバムは5作を発表。アナログ啓発活動としてヴァイナルのみのリリース•シングルなども続く。最新作は 「VEE JAYの夜ジャズ」(ビクター)「Sunaga t experience DIGS CHIEKO KINBARA~Jazz Remixies~」(CAPOTE)「BETHLEHEMの夜ジャズ」(ULTRA VIVE)「クレイジーケンバンドのィ夜ジャズ」(UNIVERSAL SIGMA)「Sunaga t experiencec/STE」(BLUE NOTE)等。多種コンピレーションの 監修やプロデュース・ワークス、海外リミックス作品含め関連する作品は延べ220作を超えた。
ひたすらラジオにかじりついていた少年時代
小学生の頃から既に音楽にのめり込んでいたという須永少年。インターネットが普及している今とは異なり、まだ見ぬ音楽に出会おうにも頼れるのはテレビとラジオだけだった。しかし、テレビで洋楽が流れることは少なく、異国の音楽に思いを馳せる少年は、夜な夜なラジオにかじりつく毎日を送っていた。
「情報がとにかくなかったんですよね。テレビでも洋楽番組はあまりなくて、あの頃はラジオから流れてくる音楽が全てでした。だから、ひたすらラジオを聞いていましたよ。その頃から良いと感じた音楽はお小遣いを貯めてレコードを購入していました」
当時DJという存在は一般的ではなかった。無類の音楽好きとはいえ、まして小学生の須永が「DJ」という職業の存在を知る由もない。須永が初めてDJの存在を知ったのは高校時代だ。
「ロンドンナイト」に魅せられた高校時代
「踊る」といえばソウルが主流だった80年代前半のディスコクラブ。そんな中、音楽評論家の大貫憲章氏が新宿ツバキハウスで主催したパンク・ロックで踊るイベント「ロンドンナイト」は、パンク、ニューウェーブ系に傾倒するリスナーを中心に爆発的な人気を誇った。パンクミュージックにはまっていた高校生の須永も、それに魅せられた者の一人である。
ロンドンナイトには、将来の日本のファッションや音楽業界を牽引することになるお洒落で音楽にも造詣が深いカルチャーエリートたちが日本全国から集まっていた。背伸びして覗いた光景はあまりにも眩しかった。
「とにかく敷居が高いイベントでした。自分なんかがその人たちに『ついていく』というのもおこがましいくらいの眩しい世界。もう、センスの次元が違うという感じでした。それでも、雑誌『宝島』を隅から隅まで読んで知識を入れてね。もう根性で通っていました」
1,000人ものオーディエンスが熱狂的に踊るフロアを巧みに操るDJ。その光景に須永は衝撃を受けた。「いつかブースの向こう側に立ちたい」と、フロアで踊っていた須永は思いを強くした。
好きなことはとことん追求する性格だった。高校三年生の時には、友人宅に居候し、毎日のようにクラブに通いつめた。 憧れであった大貫憲章門下のロカビリーDJ・ビリー北村に何度も懇願し、弟子入りも果たした。
そんな須永に幸運が訪れる。ツバキハウスからDJをやってみないかという誘いが来たのだ。 二つ返事で快諾し、須永のDJとしての活動が始まった。
しかし、現実は甘くない。 すぐに経験豊富な即戦力DJが入って来たことにより、見習いだった須永はツバキハウス系列店に回されることになったのだ。
「僕みたいな見習いは『今はちょっと雇えない・・・』となってしまいました。ツバキハウスでやれたのは7日間ぐらいかな。すぐに系列店のバーに回されちゃいました」
無給で毎日夕方4時から朝5時まで働いた
ツバキハウスの系列店を経て、横浜のディスコへと派遣された。 ここでは、一転、想像もしていなかった地獄を味わうこととなる。 この時代のDJはディスコが雇う一従業員であり、「DJ係」と呼ばれていた。レコードは基本的にディスコが抱えているものを使用していた。
須永が派遣された横浜のディスコはなんとブラックミュージックしか流してはいけないディスコだった。パンクミュージックが好きだった当時の須永にとって、ブラックミュージックは馴染みもなければ好みの音楽でもない。 その上、技術を学ぶ見習いの立場であったため給料は支給されない。無給で毎日夕方4時から朝5時まで働き続ける。 DJをしていない時は、他の従業員と同様にお酒の提供やフロアの掃除も行った。無給なので家など借りられるはずもない。友人の家に居候し、生活を助けてもらいながらひたすら修行した。精神的にも体力的にも辛い日々が続いた。
「意味のない根性試しのようなことも多くて、とにかく早く抜け出したかった。好きなロックの曲をかけるとすぐにスタッフから怒られました。それまでブラックミュージックを全く知らなかったので、店のレコードを徹底的に覚えることから始め、先輩DJがプレイしている時は必死にメモして選曲を覚えました。あとは先輩DJのサポートをしつつ基本的なテクニックも盗みましたね。それで、あまりにもお客さんがいなくなってきたら『お前まわせ!』みたいな感じの毎日」
その頃の須永にとって一筋の光明は、都内からヘルプでやってくるDJだった。当時勤めていた横浜のディスコは都内のディスコと繋がりのある店舗だったため、よく都内のDJがヘルプに来ていたのだ。須永は都内からやってくるDJにSOSを出し続けていた。
幸いにも、あるとき須永のSOSに先輩DJが反応し声をかけてくれた。青山にあるディスコ、TOKIOがDJを募集しているからやってみないかという誘いだった。TOKIOでは給料が出るらしい。 ブラックミュージックしかかけてはいけない環境で、しかも無給で半年ほど働き続けていた須永にとって朗報だった。喜んで青山TOKIOに移った。
「ここからお金を頂き、職業としてのDJが始まったので、ここが本当のスタートですね。 ただ、TOKIOでも自分が好きな音楽がかけられるほど自由ではなかったんです」
DJとしての本当のスタート
青山TOKIOは外国人のモデルやセレブたちが集まるディスコだった。しかしモデルとはいえ、ワイオミング州やテキサス州など田舎からスカウトされるアメリカ人が多かった。
「アメリカ人は主張が強くて、自分が聴きたい曲以外は頑として聞かないんですよね。こっちから色々と提案してみても、結局はヒットチャートの上位を飾るような王道アメリカンロックをかけろと頑なに言ってきました。U2やシンディ・ローパーしか知らないんですよ(笑)。ブラックミュージック地獄の次はヒットチャート地獄が待っていました 」
しかし、そんな中でも個性を発揮し、フロアを盛り上げるDJがいた。当時、六本木青山界隈で超有名だったDJ由井充だ。
「由井さんは、天才的な閃きの持ち主でした。お客さんの要望を軽くいなしつつフロアをコントロールしていたんですよね。終いにはローリー・アンダーソン(前衛エレクトロ音楽家)のリズムレスの曲でフロアをパニックに陥れるぐらい盛り上げていました。『天才っているんだなぁ』と思いました。それを目の当たりにして、DJはエンターテイナーなんだなと初めて感じました」
この前後、アメリカの音楽シーンでは新たな潮流が現れ始めていた。ヒップホップ界の名門レーベルDef Jamの登場である。Def Jamに所属していたユニットであるビースティー・ボーイズのデビューアルバム「Licensed to Ill」はヒップホップ史上初となるビルボード・チャート1位を獲得。一介のパンク好きであった若手DJ須永に転機が訪れる。
「初めて聞いた時に、これって『ブラックミュージックのパンクじゃん』と思いました。RUN DMCにも感じていたそれが確信に変わりそこから一気にヒップホップの方に加速しました」
TOKIOを出る頃にはすっかりヒップホップに傾倒していた須永。ブラックミュージック中心の箱を経由したことにも、意味があったのかもしれない。
(ビースティー・ボーイズ「Licensed to Ill」)
その後は原宿のモンクベリーズというクラブに入店する。 ブラックミュージック地獄、アメリカンロック地獄から抜け出し、自分がかけたい曲を好きなようにかけられる環境を初めて手に入れた。ヒップホップだけではなく、ヒップホップのトラックに使用されているサンプリングソース(元ネタ)も調べ、かけるようになった。
ここでは、良き先輩との出会いにも恵まれた。PA界の大御所、DUB MASTER Xからは機材、音質面での知識、選曲術を徹底的に学んだ。モンクベリーズにはMUTE BEAT、ヤン富田、いとうせいこう、中西俊夫など、今も親交の深い先輩がよく集っていた。

(原宿モンクベリーズ時代の須永)
同時期に、西麻布ではTOOLS BARやP・PICASOがオープンした。 毎日同じDJが回すのではなく、1日ごとにカラーの違うDJが回すワン・オフ・クラブが現れ始めた。そこで初めて個性を出したイベントを定期的に開催できるようになり、自分が主催するイベントも持つようになった。DJ Doc.HolidayというDJネームを名乗り開催したスケーターとラッパーのためのイベントは、いつしか平日であるにもかかわらず200名を動員する人気イベントとなった。
「Def Jamの流れで開催したイベントでしたね。スケーターやハードコアのシーンとコラボしたりもしました。時代のニーズに合っていたんだと思います」
この頃から続々とクラブが各地に展開され、DJ文化が一気に花開いた。 DJカルチャーが大きく変わりはじめている。気づいた時には、須永辰緒はその中心にいた。
「音楽に対して常に正直でいよう」
人生のターニングポイントと言える原宿モンクベリーズ。様々な出会いを与えてくれたクラブは土地の問題で閉店することになってしまった。ここで須永は自分の今後の運命を決めるであろう大きな決断を下す。
当時主流だったクラブの従業員である「DJ係」として活動するのではなく、クラブに属さないフリーのDJとして生きていく道を選んだのだ。
「当時、フリーのDJはほとんどいなくて、大貫(憲章)さんと藤原ヒロシさんぐらいだったかな。たぶん日本でフリー宣言をしたのは僕が5,6人目だったと思いますよ。」
収入も地位も保証されない世界に進む。須永の背中を押したものはなんだったのか。
「やっと自分がやりたいスタイルでプレイができるようになったんですよね。収入的には追いつかないかもしれないけど、音楽に対して常に正直でいようと思いました。ご飯を食べたいからという理由では一切やっていない。さらに音楽を追求していきたいというその一心です」
覚悟していたものの、やはり収入面での壁には苦しめられた。それでも貪欲に音楽を掘り続けた。新しく出たヒップホップはくまなくチェックし、サンプリングソースまで辿った。自然とレアグルーブにもアンテナが向いた。純粋な情熱だけで前に進んだ。
88年には「ロンドンナイト」で憧れだった高木完、藤原ヒロシをはじめ、中西俊夫、K.U.D.O.等錚々たる顔ぶれが、ソニー傘下のサブレーベルで「MAJOR FORCE」というレーベルを立ち上げた。同時に、自身が傾倒するヒップホップに未来を感じていた。
(「MAJOR FORCE」からリリースした「Club of Steel」収録アルバム「CHECK YOUR MIKE」)
須永が主催するイベントには、将来有望な若者が集まっていた。 そこから自然と音源制作も行うようになった。
「スチャダラパー、MURO君、DEV LARGE、DJ KAORIとか。様々なラッパーやDJが来ていました。そういった眠れる才能を『世に出したい!』と思って、MAJOR FORCEにもお願いしたんですけど、『いやいや、まだまだ出せるレベルじゃないよ』と言われてしまい・・・確かにその通りなんです。でも、これからが旬というか、タイミングが大事だと思ってました」
須永はプロデューサー的立ち位置で、知り合いのレーベル内にサブレーベル「RHYTHM」を立ち上げ、 YOU THE ROCK★、BOY-KEN、GAS BOYSら若い才能をプロデュースし始めた。面倒見の良い須永は個人的に彼らのサポートをしてあげることも多かった。
「お金がないといえば貸してあげたり。地方ライブで『ギター忘れた』と言うので、仕方なくギターを買ってあげたり。貸しだからなって言っても返ってきたことはないですけどね(笑)」
若い才能に投資するには、金銭的な体力が必要だった。しかし、制作を行っても自分にお金はほとんど入ってこなかった。
「当時は若かったこともあり、ビジネスモデルを分かっていなかったんです。どのようにCD、レコードが流通しどれだけ自分にバックされるかを知らないまま、情熱だけでつくっていて」
音楽に対する純粋な情熱だけでここまで駆け上がってきた須永は、ビジネス面で大きなストレスを感じるようになった。 ここでまた、人生の転機が訪れる。
「ストレスを感じたら逃げる。面倒なことがあったら関わらない。面倒な仕事には関わらない」
自身のスタンスをそう語る須永は、ラッパーであるECDと2人で続けていたユニットECD&DJ Doc.Holidayと先輩に誘われたDJイベントのレギュラーの現場だけを残して個人の音楽活動を辞め、音楽業界から足を洗うことになった。
人生で初めての転職
30歳を超えて初めての転職をした。須永が次に選んだ職業はなんとイタリアンレストランの料理人だ。
「料理はクリエイティブだし、元々好きだったんです。知り合いのレストランに無理を言って修行をさせてもらいました。本格的にイタリア料理を学び、本気で世界を目指していました。 」
下ごしらえ、包丁の使い方。料理の基礎は全てここで学んだ。
「料理ではオペレーション(手際)が一番大事。これをしている間にあれを仕込んで・・・と言ったように同時進行を極める。DJと同じです」
職が変わっても、音楽自体は大好きだった。料理人として働いていてもレコードを掘ることを止めたことはなかった。
イタリア料理の修行を始めて3年が経った。料理人としての道を着々と歩んでいた頃、宇田川町でレコード屋を経営していた同期のDJとたまたま話をする機会があった。そこで、思いもよらぬきっかけから再び人生の歯車が回り始める。
「どこか未練があり、僕が羨ましいなぁという顔をしていたのかもしれませんね。彼から『レコード屋で働かないか』と誘われました。それで・・・結局、戻っちゃったんですよね」
3年の料理人生活を経て、二度目の転職。須永はレコード屋で働き始めた。買い付けに行ったり販促のためにミックステープの制作も行なった。だが、もう一度クラブシーンに戻るつもりはなかった。ないはずだった・・・。
Organ.Barをプロデュース
ある日、レコード屋で店番していると、旧知の仲である渋谷 Bar Inkstickの社長が訪ねてきた。なんでも、宇田川町に「ラウンジ」をつくるらしい。「ラウンジ」とは今でいう「DJ BAR」のような、食事やお酒を楽しみながら、踊らずとも良い音楽に浸れる大人の空間だ。
当時ディスコやクラブが主流だった日本では「ラウンジ」という概念が広まっていなかったが、レコードの買い付けで海外に行っていたこともあり、海外のシーンに詳しかった須永は「ラウンジ」の魅力を理解していた。海外には、美味しいお酒と音楽がかかっていれば、踊らなくても楽める場所がある。そんな空間を日本につくることに可能性を感じていた。
「社長が『今日は工事で・・・』『今日は内装で・・・』と言った具合で、毎日お店に入り浸ってたんですよね。でも肝心のコンテンツが何も決まっていなかったらしく、『お前やってくれないか』と言われました。」
だが、もうDJ業界に戻るつもりはない。断って断って断り続けた。 しかし、相手も折れなかった。何度も何度も店を訪ねてきた。昔から付き合いのある先輩で、コレクターとしての趣味も合う。センスも認めている。
最終的には情熱に押された。須永はDJの手配など、コンテンツ面のプロデュースを担うことになった。今もなお宇田川町でレコード文化の変遷を見守り続ける老舗クラブ・Organ.Barの始まりである。
「蓋を開けてみたら従業員がいなく、『カウンターがいない!』『キャッシャーがいない!』みたいな状態でした。仕方ないから社長と二人でカウンターとキャッシャーを交代でやってました。話が違うじゃんって(笑)。 そうこうしているうちにレコード屋の方もできなくなってしまいまし。」
DJ須永辰緒
レコード屋の仕事で培った知識も加わり、パンク、ヒップホップ、レアグルーブ、ジャズ等、様々な音楽の関連性が把握できるようになっていた。今更パンクやヒップホップにこだわらなくてもいい。心機一転、DJネームを本名である「須永辰緒」に変え、ジャンルレスに世界中の音楽をかけた。
その中でも須永はジャズだけでフロアを沸かし、「ジャズで踊らせる」ことに熱を注いだ。
「ヒップホップを探るとサンプリングソースにあたります。サンプリングソースって本当に色々なレコードが使用されているんですよ。そうやって幅を広げているうちに、特にジャズ・ファンクのネタが自分のスタイルに合ったんです。ジャズやブラジル音楽の魅力の奥底をそこで知りました。そこから生音中心のプレイスタイルになり、主にジャズをプレイするようになりました」
また、須永のルーツであるパンクの精神も須永をジャズに熱中させた。
「パンクをかければパンクだというわけじゃない。パンクは姿勢なんです。パンクは外に向けるものではなく、内面に向かって咆哮するものなんです。だから、とてもダンスミュージックとは思えないジャズだけで踊らせるというのは凄くパンクなんじゃないかと思いました」

努力の天才
クラブジャズのパイオニアであるU.F.O.(ユナイテッド・フューチャー・オーガニゼイション)が海外に活躍の場を広げ、モンド・グロッソがアシッドジャズの礎を築く時期、須永はそれとは全く別のアプローチでジャズに辿り着いた。ジャズだけでフロアを沸かす。そんな道に自然と挑戦できたのは、圧倒的な知識量に加え、並外れた探究心があったからに他ならない。
「未だに朝起きたらかかさず世界中のデジタル音楽を聞いています。プロスポーツ選手が朝起きたら走ろうというのと一緒で。もう完全に習慣化してしまっていますね。周りに絶対に敵わないような天才がたくさんいたので、死ぬほど努力しました。自分は努力だけは天才だと思っています」
須永は、努力で培った膨大な知識と長年の経験で磨き上げた確かなセンスで精力的にジャズの裾野を広げた。伝説のミックステープと呼ばれる「Organ b.SUITE」シリーズ、国内外問わずに独自のセンスで選曲したミックスCD「World Standard」シリーズ、15作を超えるジャズコンピレーションアルバム「須永辰緒の夜ジャズ」シリーズ等、様々な作品を残した。DJ活動ではヨーロッパやアジアのイベントにも出演するなど、海外のDJシーンとも深く関わった。

(インタビュー当日は「夜ジャズ digs Venus Jazz opusⅠ(LP盤)」の発売日であった。発売初日で売り切れが続出した。)
また、人との繋がりを大事にしてきた須永の人柄が作品にも良い影響をもたらすこともあった。自身のDJ活動30周年を記念したSunaga t experienceの5thアルバム「STE」の「DIRTY 30」では、DJ Doc.Holiday時代から未だ交流のあるスチャダラパー、MURO、Zeebra、YOU THE ROCK★や、共にユニットを組んでいたECD等、名だたる面々が豪華なマイクリレーを披露した。
掘り続ける。誰よりも音楽を貪欲に掘り続けてきた男が、これからも絶えず掘り続ける。到底追いつくことはできないだろう。須永はDJシーンを牽引する存在になっていた。
次世代のDJヘ
今年でデビューから32年。須永は、今、DJとして次の世代にシーンを引き継ぐ責任を強く感じている。
「身を引くことも大事です。次の世代にパスしないといけないと本格的に考えています。それは次の世代を育てるということではなく、世代を引っ張れるDJが出て来られるように環境を仕向けるというニュアンスです。僕らは環境から切り開いてきたけど、次の世代にはその部分を端折らせてあげたいんです」
インターネットが普及した今、セルフプロデュースの方法は多様化している。次世代のDJに求められているものは何だろうか。
「例えば、ピコ太郎にはテクノの素養があった。そうでないと808(ローランド社のリズムマシーンTR-808)のあの音を使おうとは思わないです。多分元々テクノが好きだったんだと思いますよ。基礎をわかっているから音楽に詳しい人も唸らせられる。何が世にウケるのかというのは僕には分からないけど、基礎だけ持っていれば外に出ても恥ずかしくないと思うんです。だから『インクレディブルDJ’s』では徹底的に基礎を教えています 」

「DJは『基礎+センス』だと考えています。基礎は教えられるけど、センスを教えるのは難しい。でも、努力次第でセンスを磨くこともできます。僕の場合は周りに天才が集まっていたことが大きかったですね。常にその差を埋めようと努力していました。」
須永辰緒は努力の人である。そしてその努力を支えた原動力は音楽に対する純粋な興味だ。世代が交代し、クラブシーンが変わったとしても、須永は誰も知らない音源を求めてレコードを掘り続けているに違いない。須永と親交の深い日本語ラップの先駆者であるいとうせいこうはこう語る。
辰緒がガツンとわからせてくれる。DJは職業の名前じゃない。ひとつの立派なビョーキの名前なんだ。死ぬまで治らないんだぜ