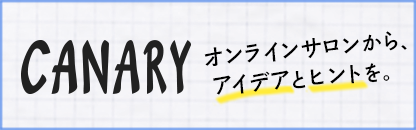須賀健太が、オンラインサロンを始めると言う。今やいろんな有名人がオンラインサロンを開設しているけれど、俳優というジャンルに限ってみれば、まだ決してそんなに多くはない。
どうして須賀健太はオンラインサロンをやってみようと思ったのだろうか。きっとそこには、エンターテインメントを取り巻く景色ががらりと変わったこの1年で感じた心境の変化があるに違いない。
今、彼が何を思っているのか。その内面を知るべく、じっくり1時間30分、話を聞いてみた。ここから綴られる約1万字のインタビューは、俳優・須賀健太が26歳の今感じる、等身大の言葉たちだ。
俳優って演じる作品がないと成り立たない職業なんだなと思った

――新型コロナウイルスの脅威は芸能界にも深刻なダメージをもたらしました。須賀さん自身も、昨年5月に上演予定だった舞台『ワケあって火星に住みました~エラバレシ4ニン~』が公演中止に。自分たちが当たり前にやっていたことが当たり前じゃなくなったという状況下でどんなことを感じていましたか。
怖いなっていうのがありましたね。あの頃は知り合いのツイートを見てもみんな「公演中止になりました」ばっかりで、これからどうなるんだろうって、すごく不安でした。そこからしばらく経って、徐々に役者を辞める人も出てきて。直接面識はない方でも、そういうリツイートが流れてくるのを見ると、しょうがないんだけど怖かったです。
――その頃からエンターテインメントは不要不急かという議論が交わされるようになりました。
僕たちはエンターテインメントを提供することで、お金をもらっていて。それができなくなると生活ができないというのは確かにそうで、正しいんだけど。でも自分たちが食えなくなるからエンターテインメントをなくしてほしくないと言ってるんだ、というふうには伝わってほしくないなというのは当時からずっと考えていました。
――どういうことでしょうか。
必要とか、不必要とかいう、その議論自体がちょっと違っているのかなと思っていて。そんな命を懸けてまで劇場やライブに行く必要はないだろうと言ってる人の気持ちもわかる。だけど、命を懸けてまで行きたい人たちがいることもわかってほしいなっていう。
極端な話、僕自身は、ここから1年間仕事がありません、その間無収入ですというのは覚悟はしていて。まあ、実際にそうなると困るんですけど(笑)。
――困りますけどね(笑)。
困るけど、でもこの仕事を選んだ以上、その覚悟はあって。
でも、そういう自分のことよりも、僕がエンターテインメントが必要だと思うのは、エンタメがないと生活している意味がないと言う人たちの気持ちがわかるからで。実際、僕を応援してくれる人の中にもそういう人がいたし。何より僕自身が舞台を観て魂が震えるみたいな経験を何度もしてきて。大げさじゃなく、生きてて良かったと感じたことが何度もあったから、やめたくないし、なくなってほしくないなと思っていました。
――ただ現実には、緊急事態宣言下でほぼすべての舞台が中止となり、多くの俳優が表現する場を失いました。その中でエンタメを求める人たちの声に応えられない歯がゆさというのも感じましたか。
ありましたね。俳優って演じる作品がないと成り立たない職業なんだなと。芸人さんなら身一つで笑わせることもできるし、ミュージシャンの方は歌や音楽で人を楽しませることができる。でも俳優は作品がないと何もできない。そこは歯がゆかったですね。
でも、そんな僕に対して応援してくださる方たちは言ってくれるんですよ、「大変だと思いますけど頑張ってくださいね」って。みなさんだってきっと大変なはずなのに、そうやって僕を勇気づけてくれる。その声に後押しされて、僕も何かやらなきゃと思うようになりましたね。
より深く僕を追ってくれる人とコミュニケーションできる場がほしかった

――そこからどんなアクションを起こしていったんですか。
インスタライブをやったり、ツイキャスを週1ペースでやったり。そしたら、「この時間が楽しみになりました」というレスポンスがたくさん返ってきて。こういう時期だからこそ、普段なら僕のインスタライブに来ないような人もたくさん来てくれて。それはすごくうれしかったです。
だからこそ、僕自身も間口を広げるというか、今まで以上に僕のことを知らない人に知ってもらうチャンスとして、この1年、いろいろ活動をしてきたんですけど、その中で少しずつ考え方も変わってきて。それが、今回、オンラインサロンをやってみようと思った理由でもあるんですけど。
――ぜひそこを詳しく聞かせてください。
ステイホームの時間が増えて、配信とかエンタメの選択肢も増えて、今はみんなが“選べる”時代になっていると思うんですね。ドラマとか映画も2倍速で観る人がいるって聞きますし。楽しむというより、情報を取り込むためにコンテンツを消費する人たちが増えてきて。それがコロナによって拍車がかかった感じがしたんです。
インスタライブをやってても、「何か質問はありますか?」って聞いたらありがたいことにたくさん質問が届くんですけど。中には、「それ、本当に俺に答えを欲してる?」というものもあって。
それ自体が悪いというわけではないんです。ないがしろにしようとも思ってないし。ただ、この先どうしたらいいんだろうと考えたときに、より多くの人に知ってもらうことも大事だけど、今僕を応援してくれている人をもっと大切にすることも必要なんじゃないかなって。その住み分けができたらなと考えるようになりました。
フランクに僕を応援したいという人ももちろん大事。だから、そこはきちんと今まで通りTwitterやInstagramで頑張っていく。それと同時に、より深く僕を追っかけていきたいと思ってくれている人のために、もっとしっかりコミュニケーションがとれる場所がつくれたらいいなって。
――その場が、今回開設したオンラインサロン「私立 須賀っ校。」だと。
まあネーミングセンスは置いておいて(笑)。学校のような場所をつくりたかったんです。
大人になって振り返ってみると、学校にいたときってやっぱりすごいエネルギーがあったなって。文化祭や体育祭もそうですけど、何気ない毎日でさえ特別で。みんなで同じ授業を受けて、飯を食ってみたいなことってあの瞬間しかないじゃないですか。特に僕は子役をやっていて、毎日学校に行けていたわけじゃないから、余計そう感じたのかもしれないけど、刹那的な良さが学校にあったなって思ったんですね。
このオンラインサロンでは、あの頃みたいにみんなが同じ方向を向いて、一緒に何かをつくり上げるようなことがしたくて。それで、「私立 須賀っ校。」という名前にしました。
――ある意味、ファンと須賀さんがクラスメイトのような。
そうそう。同じコミュニティの中にいるよというふうに感じてもらえたらうれしいなって。「私立 須賀っ校。」では部活動と題して、グッズを考えたり、YouTubeの企画を出したりしてもらおうと考えているんですけど、そんなふうにしてみんなで一緒に“須賀健太”をつくり上げていけたらなと。
僕はいずれ演出とか監督もやってみたいと思っているので、まずここで何かちっちゃい映像もつくってみたい。それを、「私立 須賀っ校。」のメンバーで一緒につくれたら面白そうじゃないですか。
月に1回、“全校集会”という名前で配信もやるつもりで。そこではみんなからのコメントを拾いながら、インスタライブよりもぐっと密度の濃いやりとりがしたいですね。
――ソーシャルディスタンスが叫ばれるようになって、より“つながり”を求める人が増えたように感じています。その中でコミュニティに属する安心感というのは大きいですよね。
僕らの仕事って、よく“夢を売る仕事”だと言われると思うんですけど、こういう苦しい時期に一緒になって不安になってたら、自分たちのことを“夢を売る仕事”だって胸を張って言えなくなっちゃう気がしたんですね。むしろ今こそ僕らの頑張りどき。厳しいときだからこそ、そんなこと関係ないくらい楽しんでもらえることがしたいし、エンジンかけてやんなきゃなって気持ちはあります。
――芸歴が長いからでしょうか。須賀さんは非常に“夢を売る仕事”という意識が強い気がします。
僕が憧れていた人たちが、そういう人たちだったからだと思います。香取慎吾さんとか、森田剛さんとか、見ていてすごくカッコいいなと思ったし、ワクワクしたし。僕自身、現場にいるのが何よりも楽しかった。だから、自分もワクワクするという感情は大事にしたくて。
小さい頃から現場が好きなんですよね。大人たちがワイワイしながら、ものをつくっているあの感じが大好きで。この仕事を続けたいと思ったのも、あの空気感が好きだったから。サロンもそうなのかもしれない。みんなで一緒にワイワイ言いながらものづくりができる。そのワクワク感を、オンラインサロンでみんなと共有できたらなと思います。
応援してもらえることが当たり前ではないという意識はすごくある

――サロンのメンバーを、一緒にものづくりをするクラスメイトと定義づけるとしたら、そこではオープンな場では見せていない須賀さんの素顔も見られると考えていいでしょうか。
そうですね。自分の弱い部分というか、隙のある部分というか。そういうのって誰にでも見せられるものではないし、みんなに見せても面白くないと思うから。そこをいいと言ってくれるコミュニティになったらいいなと思うし、そういう場所にしていきたいです。
俳優って役を通して好きになってもらうことが多くて。もちろんその役を演じている間応援してもらえるだけでもありがたいことだけど、そこからさらに一歩踏み込んで、須賀健太という人間を好きになってもらえたらいいなというのは、よく考えます。
――難しいですよね、俳優を応援するのって。役ありきで好きになると、違う役を演じているときに「あれ? ちょっと違う…」となってしまうこともあるし。
その気持ちもすごくわかるんですよ。役を好きになってくれたファンの方って、その作品を演じている期間の熱量はものすごく高いけど、その役を演じ終えたあともついてきてくれるかといったらまた別で。でもそれは全然悪いわけではないから。
僕自身もいろんな作品をやってきて、その難しさを実感しているからこそ、応援してもらえることが当たり前ではないという意識はすごくあります。Twitterとかで、最近この人からリプないなとか結構さみしいし(笑)。
――やっぱり誰からリプが来るとか覚えるんですね(笑)。
覚えます(笑)。本当、ひとつひとつのリプに僕らはパワーもらっているから。その分、ちゃんと返さなきゃなって思うし。
――芸能人のあり方も変わってきました。昔は、素を見せないのがいいとされていましたが、今はその人の人間性までわかる人の方が愛されるようになっていたり。
本当は憧れるんですよ。そんなふうに私生活を見せず、作品だけで勝負する俳優さんとかカッコいいと思うし、自分もできることならやってみたいけど、俺には無理だなとも思うし(笑)。
今は、全部を見せて戦わないといけない時代なのかなって。何が正解かわからないけど、もし自分がファンだったらこの人を応援したいなって思えることを、僕はどんどんやっていきたい。「私立 須賀っ校。」では、役と離れた僕のパーソナルなところをもっと見せていきたいですね。
香取さんに初めて会ったとき、「おっはー」って言っちゃったんです(笑)

――では、ここからは改めて須賀さんのパーソナルな部分を聞かせてください。須賀さんといえば、やっぱり子役時代のことが印象に残っている人も多いと思うんですね。須賀さんの名が一躍世に知れ渡ったのは、2002年に放映されたドラマ『人にやさしく』。当時のことを覚えていますか。
覚えています。ちゃんとした台詞のある役をもらうのが、あれがほぼ初めてで。難しいこととかわかんなくて、とにかく現場に行ったら慎吾ママがいるっていう感覚だったんですよ。今でもすっごい覚えているのが、衣装合わせで初めて香取さんにお会いしたとき、普通、「おはようございます」じゃないですか。でも、僕は「おっはー」って言っちゃったんです(笑)。それくらい何もわかっていなかった。遊びに行ってる感覚でした。
――『人にやさしく』は平均視聴率20%超のヒットドラマ。須賀さんは、香取慎吾さん、加藤浩次さん、松岡充さんらに育てられる五十嵐明という男の子を演じました。ドラマの中心的な存在で、出番も多い。学校での反響もすごかったんじゃないですか。
1話が放送された次の日は、教室の前に人だかりができていました。何かあったのかなと思って教室に入ったら、みんなが僕を見にきていたっていう(笑)。当時は月9全盛期。ドラマの影響力ってすげえな!と思ったし、え〜面白いって感じで、ちょっと他人事みたいというか、能天気に受け止めていました。
――須賀さんの演技に「天才子役」という評価が集まりました。そうした絶賛の声をどう感じていましたか。
よくわからなかったですね。天才というものが何かもわからないし。演じているつもりがなかったから。もうできないですけどね、あんな芝居は。
――やっぱり今と違うんですか。
違います。あの頃は、須賀健太演じる五十嵐明ではなくて、五十嵐明っていう人になっていたから。そこは子どものすごいところですよね。何も意図せずそうなれている。もともとごっこ遊びが好きな子どもで。小さい頃から今日は戦隊ヒーローとか、今日は消防士とか、そんなふうになりきって遊ぶのが好きだったんですよ。お芝居は、その延長線上という感覚。当時、あの3ヶ月は「君は五十嵐明だよ」と言われたら、純粋にそうなりきっていました。
――仕事という感覚ではなかった。
なかったですね。打ち上げのときに、香取さんと加藤さんと松岡さんの3人に会えなくなるのが嫌で泣いていました(笑)。それくらい、当時は仕事としての認識がなかったというか、何にもわかっていませんでした。
高校に入って、「天才のわりに仕事少ねえな」と思った

――そんな須賀さんが、役者としての自覚に目覚めたのは?
10歳のときに主演をさせてもらった『花田少年史 -幽霊と秘密のトンネル-』ですね。水田(伸生)監督が毎回、「明日はこのシーンをやるからどういう動きをするか考えてきて」って宿題をくれて。自分の考えてきたものが良かったら採用されるし、良くなかったらちゃんと何が良くないのか言ってもらえる。そうやって考えたものが評価してもらえることがうれしくて。つくったものをお客さんが観て楽しんでくれる。その光景を目の当たりにしたとき、自分はすごいことをやっているのかもしれないって初めて思いました。
―ー当時は須賀健太という名前の頭に常に“天才子役”というフレーズがくっついていました。自分自身が“天才ではない”と自覚したのはいつ頃ですか。
高校生の頃ですね。天才のわりに仕事少ねえなと(笑)。
――子役あるあるですが、やっぱり高校に入ると仕事がなくなるんですね。
そうですね。だからすっごい嫌でした、“天才子役”って言われるのが。じゃあなんでこんなに演じる場がないんだって。“天才子役”って誰が言ってるんだ、言ってるやつ連れてこいって思ってました。本当に俺のこと知ってるのかよって、尾崎豊みたいな気持ちでした(笑)。
――窓ガラスは割りましたか(笑)。
割らなかったです(笑)。そういうことはちょっと怖くてできなかった(笑)。
――もっと仕事がほしいという話は、事務所の方にもしていたんですか。
言ってましたね。その当時はまだ前の事務所で。これまでやってきた作品もあるから、今までの実績が低く見られないような仕事を選ぶ感覚があったんだと思うし、それも今なら大切なことだとわかるんですけど。僕としては何でもいいから仕事がほしいっていう感じで。そこがちょっとズレていたというか、もどかしい感じはありましたね。
――また高校生という時期が微妙なんですよね。ちょうどこれから売り出しにかかる新人が出てくる時期だから。
学生役とかで注目される子たちがどんどん出てきて。僕はと言うと、芸歴が長い分、現場でも中堅扱い。芝居をしても、「はいそれでオッケーです」で終わり。誰も何も言わないんです。僕としてはもっと雑に扱ってくれてもいいのに、変に気を遣われてて。監督からオッケーと言われても、「本当にできているのかな?」ってずっと不安だったし、「この人は天才子役と言われていたときの僕を見ていいねって言ってるのかな?」って、自分でもどうしたらいいのか全然わからなくなっていました。

子役のイメージから脱皮することは難しい。多くの先輩たちが通ってきたように、10代の須賀健太もその壁に直面していた。大きな壁の前でもがきながら、彼はどうやってその壁をよじ登っていったのか。同世代の俳優を見て、なぜ自分は呼ばれないんだろうという嫉妬心とどう向き合いながら、今、新しい一歩を踏み出そうとしているのか。
この先のインタビューは、オンラインサロンメンバー「須賀っ校。」限定でお読み頂けます。