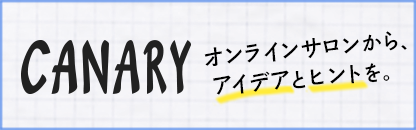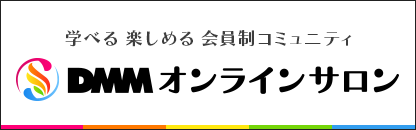本日9月1日は「防災の日」です。2025年現在、取り巻く環境も変わってきてるし、防災知識にも“アップデート”が必要なはず…!
そう思って専門家に「最新の防災術」を聞いてみたところ…本当に大切なのは、今も昔も変わらない“地道な基本”だということが見えてきました。
とはいえ、トイレ事情やペットとの避難、情報災害への備えなど、現代だからこそアップデートすべき新しい知識も確かに存在します。
今回は、DMMオンラインサロン内にて「消防・防災を学べるコミュニティ」を運営する専門家・よろずさんにお話を伺い、防災の「変わらない本質」と「変えるべき新常識」を学んできました!

運動急性腎不全をきっかけに消防職員を退職。その後リフォーム業やインスタ運営、電気工事士など様々な仕事を行う。サロン運営のほか、雑誌「近代消防」内で記事を連載するなど、消防関係者が気軽に知識を学べるために色々活動中。
あなたの家は安全?防災の第一歩は「避難」の常識アップデートから
――まずは近年の防災グッズについて聞かせてください。最近、家電量販店などでポータブル電源をよく見かけますが、やはり近年の防災において重要になっているのでしょうか?
確かにポータブル電源の重要性は増しているかと思います。ただし必要性を考える前に、まず大前提として『在宅避難するのか、避難所へ行くのか』を決めなければいけません。その判断基準となるのが、今お住まいの建物の建築時期です。
――建築時期ですか?
はい。実は建築基準法によって、建物の耐震基準は大きく異なります。
・1981年(昭和56年)以前:旧耐震基準が適用されている1981年5月以前の建物は、震度6以上の耐性は想定されていません。このため、1981年代の建物のお住まいの場合は、大地震が起きたときに倒壊リスクがあります。
・1981年~1999年:新耐震基準が適用されており、
・2000年以降:2000年基準が適用されており、
つまり、2000年以降に建てられた建物であれば倒壊リスクが低く在宅避難が可能なケースが増えてきます。そうなると、ライフラインが止まった際に生活を維持するための電気、つまりポータブル電源が重要になってきます。
――なるほど。まず自分の家の安全性を知ることが先なんですね。
その通りです。その上で、国土交通省が公開している『ハザードマップ』を必ず確認してください。洪水、土砂災害、津波など、自分の住む地域にどんなリスクがあるかを事前に把握することで、在宅避難が可能か、避難するならどこへ向かうべきかが見えてきます。
まずは自宅の築年数と地域のリスクを確認し、「自分はどこへ避難するのか」を具体的に決めておくこと。それが、現代の防災のスタートラインと言えるかもしれません。

もちろん、技術の発展により性能も上がったポータブル電源は持っておいて損はありません!ただこちらも補足すると、機種によっては買って満充電のまま放置しておくと、いざという時に本来の性能を発揮できないことがあります!
月に一度は使って空にするなど、定期的に充放電のサイクルを繰り返して、バッテリーを最適な状態に保っておきましょう。
地震、火災、豪雨…「複合災害」から身を守るために知っておくべきこと
――最近は、地震と同時に火災や津波が起きるなど、複数の災害が重なる「複合災害」も増えています。
まず複合災害の危険性でよく挙げられるのが、地震と火災のセットです。大規模な災害発生時、消防の力だけでは対応しきれないのが現実です。そこで重要になるのが、地域住民による『自主防災組織』の存在です。
――自分たちで消火活動や救助を行っているということですか?
はい。自主防災組織では、初期消火のための資機材を保有していたり、救助訓練を行っていたりします。建物の倒壊に巻き込まれた場合、助けられるのは公的機関ではなく、隣近所の人かもしれない。
『自分たちの街は自分たちで守る』という意識が、複合災害の被害を最小限に食い止める鍵になります。
――近年ですとAI技術の発達によるSNSでのデマなど「情報災害」も怖いですよね。
災害発生時、不安から様々な情報に振り回されがちですが、頼るべきは公的機関の発信する情報です。特に、気象庁の『キキクル(危険度分布)』は、大雨による土砂災害や洪水の危険度がリアルタイムで地図上に表示されるので、避難のタイミングを判断するのに非常に役立ちます。
SNSは、助けを求める際に身近な人に連絡するツールとしては有効ですが、不確定な情報に惑わされないためにも、災害発生直後は『市のホームページ』『気象庁』などの一次情報にあたることを徹底してください。

ペット、トイレ、備蓄…現代のライフスタイル防災術
――その他に、今の時代だからこそ気を付けるべき点はありますか?
細かいですが、重要なアップデートがいくつかありますのでまとめてご紹介しますね。
1.備蓄は「飲み慣れた水、食べ慣れたもの」を
5年保存水などを備えるのも良いですが、普段飲み慣れない水を飲むと体調を崩す人もいます。おすすめは、普段から消費している水や食料を少し多めにストックし、使った分だけ買い足していく『ローリングストック』です。これなら、ストレスの多い避難生活でも普段と近い食生活を送ることができます。
2. 「タンクレスのトイレ」は停電時に注意!
最近増えているタンクレスのトイレは、電気で排水弁を動かしています。停電すると、お風呂の残り湯などを流し込んでも排水できないんです。説明書を確認し、停電時の手動での排水弁の開け方を必ず覚えておいてください。それから、災害時は1週間程度トイレが使えない可能性もあるため、簡易トイレを用意しておくと良いでしょう。

3. ペットとの避難は「自治体のルール」を確認
ペットを飼っている方も多いとは思いますが、災害時には避難所へ一緒に避難できるか、事前に住んでいる自治体に確認しておくことが不可欠です。
最近は『ペット防災』に関するガイドラインを設けている自治体も増えていますので、一度ホームページなどを調べてみてください。
防災に裏技はない。地道な「知る」と「備える」が命を救う
ーー「時代の変化で大きく変わった!」を予想していたのですが、大きく気をつけるべきことは案外変わってない印象ですね。
はい、テクノロジーは進化しましたが、防災にキラキラした裏技はありません。
一番大切なのは、災害に巻き込まれない場所に住むこと、そして自分の住む場所のリスクを知り、それに合わせて備えること。この地道な準備が変わることはありません!
「キラキラした裏技はない」――よろずさんのこの言葉が、防災の本質を物語っていました。
もちろん、時代と共にアップデートすべき知識はあります。しかし、その土台にあるのは、自分の足元のリスクを知り、備えるという地道な繰り返し。
みなさんも防災の日をきっかけに、まずはお住まいの地域のハザードマップを確認してみる。そんな確実な一歩から、身を守る準備を始めてみませんか?
#防災の日 #ハザードマップ #よろづFD