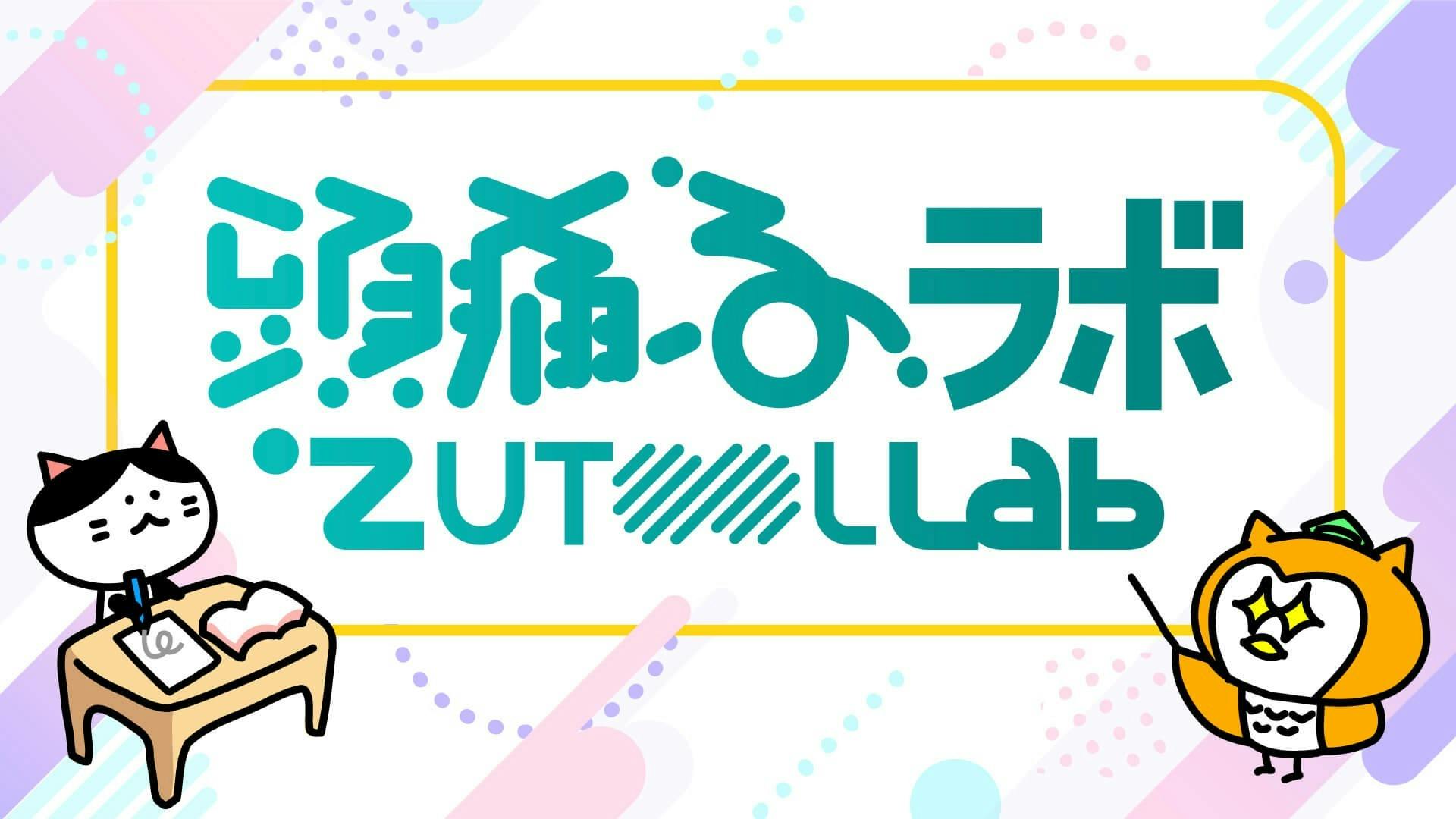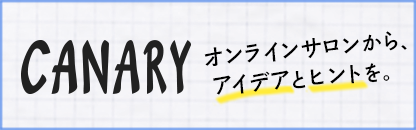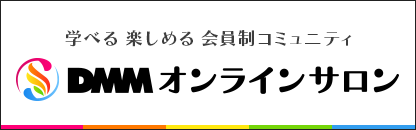今日は天気が悪くて頭が重いな……。そんな多くの人が抱えている気圧や天気による不調を、「気象病」という常識として世の中に広めてきたのが、2013年に誕生したアプリ「頭痛ーる」です。
2300万ダウンロードを超えるまでに成長した「頭痛ーる」は、それまで確かなエビデンスがなかった気圧と体調の関係を、膨大なデータで医学的に証明してきました。SNSでは日々、「頭痛ーる」の公式アカウントを通じて自分の体調の変化について発信する人々の声も増えています。
そんな「頭痛ーる」が開設したのが、オンラインサロン「Zutool Lab(頭痛ーるラボ)」です。今回はこのサービスに関わる株式会社ベルシステム24の岩見統之さん、安中朋哉さん、保母久美子さんにお話を伺いました。
「迷信じゃないの?」からのスタート。頭痛ーる12年の軌跡
――私もX(旧Twitter)で「頭痛ーる」さんのアカウントをフォローしていて、なんとなく頭が重いなと思った時にアカウントを確認するのが癖になっています。
岩見さん:そう言っていただけると嬉しいです。頭痛ーるは「痛みの予測で日々の暮らしを快適に」をコンセプトに生まれたサービスで、今年で12年目を迎えました。
気象病は、気圧や気温、湿度など天候の変化に伴って起こる体調不良の総称といわれます。人間の体は通常、外部の気圧や気温の変化に適応していますが、ストレスや疲労などで自律神経やホルモンのバランスが崩れていると、その調整が難しくなることがあります。
近年は、耳の奥にある内耳が体の平衡感覚を担い、気圧の変化を感じやすい部位の一つとして注目されています。これが刺激となり、自律神経のバランスが乱れることで片頭痛やめまいなど既往の症状が出やすくなる場合があります。
ただし、影響の程度には個人差が大きく、すべての症状や病気が気圧変化だけで説明できるわけではありません。

事業部長 岩見統之さん
――「気象病」というと頭痛のイメージが強いですが、それだけではないんですね。
岩見さん:頭痛は最も身近な症状のひとつですが、めまいやだるさ、気分の落ち込み、関節痛、古傷の痛みなど、症状は人によって異なります。最近注目されている、めまいや朝起き上がれなくなるなどの症状が出る「起立性調節障害」も、気圧との関連が注目されています。
安中さん:気象病の興味深い点は、多くの人は「低気圧」で不調を訴える一方、私のように天気が回復して「気圧が上がる時」に頭痛が起きる方もいらっしゃるんです。頭痛ーるのデータを見ても、少数ですがそういった声が集まってきています。
岩見さん:気象病の引き金は、大きな気圧の上下動だけではありません。例えば、遠く離れた東南アジアの海で台風が発生するタイミングに合わせて、体調を崩す人がいます。台風の発生によって生じる、「微気圧振動」という細かな気圧の変化がその原因です。
――気圧の低下や上昇、さらにはわずかな変化でも体調に影響を及ぼすんですね……。
安中さん:多くの人々は、昔から気圧に伴う頭痛や体調不良をなんとなく理解していたと思います。しかし、実は「頭痛ーる」をリリースした時点では、「気圧と頭痛が関連しているなんて迷信なんじゃないの?」と思われるほど医学的なエビデンスが少なかったんです。
医師の方々でさえ、気象病の存在は認識しつつ「声高に言うと叩かれるんじゃないか」という雰囲気がありました。
――その怪しさをどうやって乗り越えていったのですか?
安中さん:キャラクターの力が大きいです。「頭痛ーる」にはふくろう博士(ひろし)、マロ、てるてるネコというキャラクターがいます。それぞれ、科学的な根拠が弱い中でも気象病を受け入れてもらいやすくなるよう、親しみやすいデザインを心がけました。

この子たちが大人気で、クラウドファンディングでキャラクターのぬいぐるみを作ったところ、大盛況だったんですよ。
ちなみに、キャラクター設定にもこだわりを持たせました。例えばマロは、「頭痛ーる」のキャラクターでありながら頭痛持ちではありません。症状のつらさを表現するイラストは分かりやすい反面、見ている側も気持ちが引っ張られてしまう。だから、マロにはあっけらかんとしていてもらって、ユーザーさんがつらい気持ちにならないように配慮しました。
キャラクターのストーリーもしっかり作り込みました。結構重めな設定なので、Xでストーリーを読んだ方が「いつもヘラヘラしてると思ってごめんね……」とつぶやいているのをたまに見かけます(笑)。
――マロ、大荒れの天気でお母さんを亡くしているのですね……。そのことがきっかけで、博士がマロを引き取ることになってるなんて。これはぜひ、読者の皆さんにも読んでみてほしいです。
安中さん:キャラクターたちには、ただの癒やしではなく、気象病について解説したり、ユーザーに寄り添ったりする役割を持たせています。そうした世界観を丁寧に作ることで、怪しいという印象を少しでも和らげ、サービスのメッセージをソフトに届けていきたかったんです。

デザイン統括/マネージャー 安中朋哉さん
岩見さん:こうした活動のおかげで、アプリの累計ダウンロード数は2300万を超えました。アプリでは日々の頭痛記録を取ることで、天気の変化と自分の体調がどう連動しているのかをチェックできます。
そうして集まった痛みの記録は、累計で8300万行を超えました。ユーザーさんたちが日々記録してくださった「痛み記録」こそが、私たちの最大の財産となっています。この膨大なデータを頭痛学会の先生方と一緒に分析し、2023年2月、ついにアメリカの権威ある医学ジャーナル『Headache』に論文が掲載されました。
この論文は、2023年、2024年で最も多く他の論文に引用されるなど、世界中の研究者から注目を集めました。ユーザーの皆さんのおかげで、気象病の立証という大きな一歩を踏み出せたんです。
最近では、「頭痛ーる」はアロマオイルや枕のコラボ販売のほか、スマートウォッチ「Fitbit」と連携した健康の可視化を進めています。ペットの体調も気象によって変化することがわかってきたので、ペット専用の健康管理デバイスとのサービス連携なども行っています。
頭痛に悩む人の「知る」「相談する」「ケアする」を支えたい
――多岐にわたって活動している中、なぜオンラインサロンを始めたのですか?
岩見さん:サービスが成長するにつれて、私たちの役割が変化してきたことが大きなきっかけです。
これまでは気圧を「予測」し、痛みを「記録」し、それを「振り返る」という機能が「頭痛ーる」の中心でした。しかし、ユーザーさんの悩みはもっと複雑です。例えば街頭調査をすると、頭痛の最大の原因は「ストレス」と回答する方が一番多い。他にも、ホルモンバランスや睡眠、食事などさまざまな要因が絡み合います。
そうなると、アプリで気圧の情報を提供するだけでは、根本的な解決には至りません。これからの「頭痛ーる」は、自分の状態を「知り」、専門家に「相談」し、適切に「ケア」するというサイクルを回せるプラットフォームになる必要があると考えたんです。
ただ、そのすべてをアプリ内で完結させるには無理がありました。それに医療に関する情報は、よりクローズドで双方向性のある場でのコミュニケーションが適していると感じています。
安中さん:医師の先生方も同じ悩みを抱えています。「本当はこういうことを患者さんに伝えたいけれど、15分という短い診療時間では伝えきれない」という話をよく聞きます。
岩見さん:そこで考えたのが、オンラインサロンというクローズドな場での情報発信です。例えば、オンラインサロンの中で、臨床現場の先生方に「実際にこの薬を処方したら良くなったよ」といったリアルな事例を話してもらう。
ユーザーさんからも、普段は聞きにくいような質問を気軽に投げかけてもらう。そういう垣根のないコミュニケーションができる場を作りたかったんです。

――「Zutool Lab」にはどのような方々が集まっていますか?また、これまで提供してきたコンテンツで特に反響が大きかったものはなんですか?
保母さん:9割が女性で、年代もアプリのユーザー層とほぼ同じです。加えて、オンラインサロンに参加される方は健康への意識が非常に高い方が多いです。
特に反響が大きかったコンテンツは、Zutool Labで提供している「WKRNⓇ(ワカルン)」という健康意識診断システムです。24の質問に答えると、「RSHA(健康エリート)」「IZLU(ながら健康活用者)」などに分類され、自分の健康意識の特徴を知ることができます。
健康意識16タイプ診断『WKRN(ワカルン)Ⓡ』 – DMMオンラインサロン
ちなみに、サロンメンバーさんは「ISHA(鋼の健康管理人)」「ISLA(健康リアリスト)」という、正しい情報を自分なりに取捨選択して健康に向き合うタイプの割合が多かったです。
――どちらも「健康ガチ勢」であることがわかる名称です。私も試してみたくなりました(笑)。
保母さん:他には、島津智一先生という頭痛専門医にご登壇いただいた「片頭痛は治せる」というセミナー動画は、非常に好評でした。最近では、個々の症状に応じた薬もどんどん開発されています。
島津先生は「片頭痛を感じたら迷わず病院に来てください」とおっしゃっていて、それを聞いたサロンメンバーさんから「病院へ行く勇気をもらいました」という声も届きました。

マーケティング統括/マネージャー 保母久美子さん
――身近な病気だからこそ、「頭痛ごときで病院なんて」と思ってしまう人は多いのかもしれません。そうした風潮を変える役目を、「Zutool Lab」は担っているのですね。
岩見さん:私たちはサロン内で、頭痛学会に所属されている専門医のリストもご案内しています。情報を届けるだけでなく、具体的な「ケア」のアクションにつなげるところまでサポートするのが、サロンの大きな役割だと考えています。
目指すのは「正しい医療に、正しくつながる社会」
――今後の「頭痛ーる」サービス展開や「Zutool Lab」運営の展望について教えてください。
岩見さん:「頭痛ーる」については、9月1日に大きなニュースが発表されました。株式会社ヘッジホッグ・メドテックがこのサービスを承継するとともに、当社と資本業務提携を結ぶことになったのです。
https://www.bell24.co.jp/ja/news/holdings/20250901/
ヘッジホッグ・メドテック社は、片頭痛治療用アプリや頭痛AI診断などを開発・提供しています。「頭痛ーる」の膨大な記録と、彼らが持つクリニックでの診断記録を統合することで、今まで以上に医学の発展に貢献できることでしょう。
安中さん:私たちの使命は、頭痛に悩むユーザーさんを「正しい医療」に「正しくつなげていく」ことだと考えています。
今、世の中にはさまざまな情報が溢れていて、中にはエビデンスのない独自の治療法を勧める声もあります。そんな中、10年以上をかけてここまでサービスを広げてきた私たちには、ユーザーさんたちを適切な医療へ導いていく責任がある。今回の提携は、そのための大きな一歩です。
――医療との連携を深めていく中で、オンラインサロンはどのような役割を担うのでしょうか?
岩見さん:「Zutool Lab」はより一層、ユーザーさんが知りたいコアな気象病情報が集まる場所としての価値を高めていきたいですね。地域によっては専門外来が近くになく、十分な医療を受けられない方もいらっしゃいます。そうした医療格差を、オンラインの力で少しでも埋めていきたいです。
安中さん:同時に、このオンラインサロンをメンバーさんと一緒に作っていきたいと思っています。この12年間、ユーザーの皆さんと一緒に「頭痛ーる」を育ててきたように、その関係性をオンラインサロンでも実現していきたいです。
「次のクラウドファンディングでどんなグッズを作ろうか」といった企画会議もやりたいですね。そうやってコミュニケーションを重ねていく過程で、一人でも多くの人が天気による不調に振り回されず、快適な毎日を送れる社会を目指していきたいです。