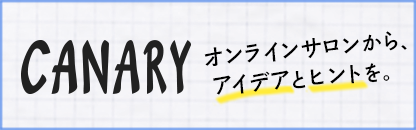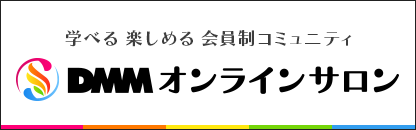全国各地の地方に眠る商品を発掘し、さらなる販路拡大を支援する地域創生プロジェクト「にっぽんの宝物」。商品の磨き上げを目的としたセミナーに加え、地方大会から全国大会、そして世界大会へとステップアップしていくグランプリ形式を採用しています。この段階的なプログラムを通じて商品はさらに磨き上げられ、数多くの素晴らしい商品が誕生しつづけています。「にっぽんの宝物」で磨き上げられた商品は、人気YouTubeチャンネル「令和の虎」「通販の虎」などで紹介される他、海外での販売も進められています。
そして今回、全国的な取り組みをさらに広げ、地域を問わず参加できる機会を提供するため、オンラインサロン「にっぽんの宝物 オンラインセミナー 2025-2026」がスタート。代表の羽根拓也さんに、「にっぽんの宝物」にかける想いやオンラインサロンを開設する狙いについて伺いました。
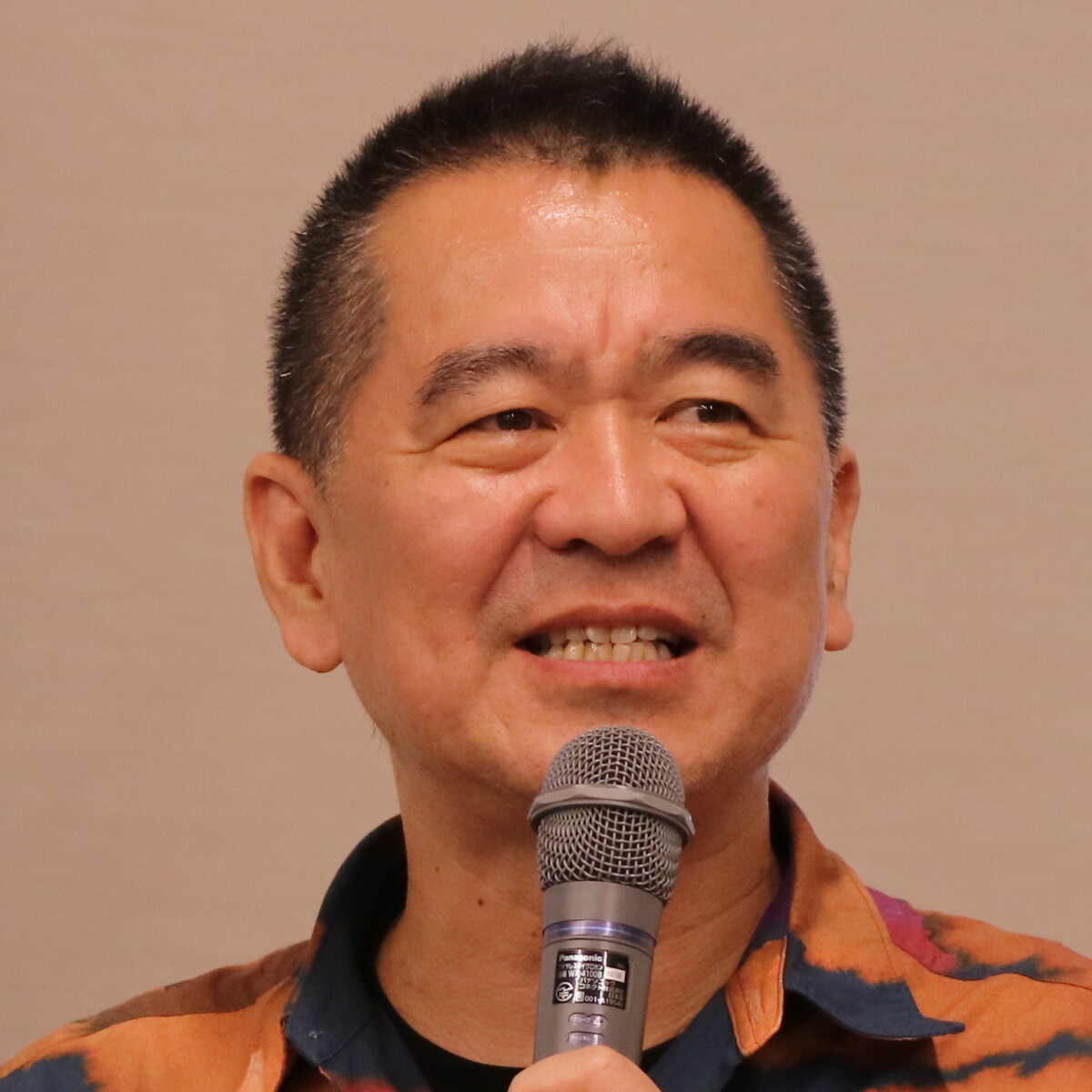
90年代、ペンシルバニア大学、ハーバード大学で日本語を指導。ハーバード大学より優秀指導証書を授与される。日本に「アクティブ・ラーニング」式の教育を広げた第一人者。文科省の国立大学新学部の選定委員等を歴任。ソニー、パナソニック等の大手企業で人材育成、商品開発の指導を行い、高い評価を得ている。にっぽんの宝物代表として、全国の事業者、数万人に指導を行い、多数のヒット商品の創出支援を行ってきた。
地域の原石をさらに輝かせる「にっぽんの宝物」の歴史

――「にっぽんの宝物」はどのような活動をしているのですか?
「にっぽんの宝物」は2009年、産官学連携のモデル校である山口大学で実施したセミナーがきっかけで始まりました。僕はこういう仕事をよく引き受けていましたが、普通にやっても面白くないなと思ったんです。
当時、僕は仕事で海外と日本を行き来していました。そこで目にしたのは、少子化などで日本の地方が寂れていく裏腹に、海外では日本食への評価がどんどん高まっているという乖離でした。
このギャップを埋められないかと考えた時、地方の課題は「学ぶ機会が少ないこと」だと感じていました。地方には、昭和の時代からずっと同じ商品を同じ製法で作り続けている事業者さんがたくさんいます。
それらは決して悪いものではありませんが、時代に合わせて変化・進化ができていない。僕が今泊まっている旅館のお土産物屋さんにも、正直「これは誰も買わないだろうな……」という商品が並んでいたりします(笑)。
――私も田舎出身なのですが、たしかに地元のお土産屋さんあるあるかもしれません。
そこで僕は、一次産業の農家、二次産業の加工業者、三次産業の旅館・道の駅などまったく違う分野の人たちが出会い、話し合うセミナーを実施しようと考えたんです。
農家さんや漁師さんも、最終的に消費者の口に入るわけですから、旅館やレストランといった三次産業の方と話した方が良いものが生まれるはず。でも、そういう機会はほとんどありません。特に田舎の狭い世界では、お互いに「あんたの商品はこうした方がいい」なんて言えませんから、自分の発想だけで頑張るしかない。
そんな状況を打破するために始めたセミナーを通じて、良い商品が徐々に生まれていきました。すると、高知市役所からも同じ取り組みをやってほしいと依頼されました。そこで僕たちは、「交流会セミナーだけで終わらせず、グランプリもやりましょう」と提案したんです。
――グランプリ。優劣をつけるのが目的でしょうか?
いえ、一番の目的は「締め切り効果」です。成果発表の場という締め切りを設けることで、より真剣に商品づくりを頑張れるようにしたいなと。この取り組みによって、商品の磨き上げの速度と完成度を格段に高められるようになりました。
すると、グランプリで選ばれた商品が、地元のメディアに取り上げられるなどスポットライトが当たり、次々と売れ始めるという現象が起きました。その動きが高知県、千葉県、宮崎県などと飛び火していき、2016年には初の全国大会を開催できるようになりました。
全国まで来たなら、次は世界だろうと(笑)。僕はもともとアメリカのハーバード大学で教えているし、アジアにも広いネットワークがあります。海外で日本食の評価が高まっているなら、いっそ海外の方から直接フィードバックをもらった方が良いだろうと考え、シンガポールのシャングリ・ラ ホテル と組んで世界大会を始めたんです。
これが非常に効果的で。地域大会から全国、世界へとステージが上がるにつれて、参加者の皆さんの「視座」が変わっていきました。

――視座が変わったというと?
例えば、世界大会でグランプリを獲った長崎県のお茶農家さんが、現地のバイヤーでもある審査員に商談の場で「あなたの商品は無農薬ですか?」と聞かれたんです。日本では農薬について比較的緩いですが、海外、特にアジアの富裕層向けマーケットでは非常に厳しい。
日本では言われたことのない言葉を投げかけられ、農家さんは「海外ではそういう視点で商品を見るのか」と衝撃を受けたそうです。そして帰国後、3年かけて有機農法に切り替えていくことで、海外進出を果たしました。外の世界に出ることで、初めて触れた価値基準を通じて、商品をブラッシュアップできたわけです。
「宝物」とはずばり「売れる商品」であること
――「にっぽんの宝物」は、「地方の原石が日本の宝物に」という言葉を掲げています。羽根さんが定義する「宝物」とは、具体的に何を指すのでしょうか?
それは明確で、「売れる商品」のことです。これは「未来に残したい文化」といった、きれいごとを言いたいわけではありません。むしろ逆で、売れていないから、未来に残せたはずの宝物がどんどん消えていっているのが今の日本の地方の現実なんです。
僕が生まれた奈良県の十津川村は、かつて1万人いた人口が今や3,000人を切りました。人口が3分の1になれば、当然、お店の売上も落ちて事業が続けられなくなり、ますます人が外に出て行ってしまいます。
この流れを断ち切るためには、「商品が売れる」ことが必須なんです。例えば、2016年のグランプリで初代チャンピオンになった「田野屋塩二郎 シューラスク」は、僕らのところに来たときは従業員20人ほどの小さな会社でした。しかしグランプリを獲ってから売上をぐんぐん伸ばし、今では年間6億円を売り上げる商品に成長しました。今では工場を新設し、従業員は200人を超えています。
磨き上げた商品が、打ち出の小槌のようにお金を生み出し、地元の雇用を創出する。これこそが、僕らが目指す「宝物」の姿なんです。
――宝物自体が、地域経済そのものを支えるようになるのですね。
だからこそ、僕らたちは商品の磨き上げを通じて売上を上げることに徹底的にこだわります。
人気YouTubeチャンネル「令和の虎」のフランチャイズ番組である「通販の虎」はご存知ですか?この番組では、「にっぽんの宝物」の歴代チャンピオンたちの商品が続々と紹介されています。
いずれの商品も非常に評価が高く、今年8月に放送された「田野屋塩二郎の塩」の回は大きな反響を呼びました。
他にも、香港のスイーツ会社と組んで年商が150倍になったお茶農家さんのような、「世界の宝物」になった事例もあります。このように、「にっぽんの宝物」を通じて、地方の原石を全国レベル、世界レベルのヒット商品にしていくことを僕たちは目指しています。
なぜ今、DMMでオンラインサロンを始めるのか
――今回、DMMオンラインサロンという新しい形を選んだのはなぜでしょうか?
一番の理由は、僕らがこれまで出会えなかったタイプの事業者さんに出会える可能性があると感じたからです。「令和の虎」や「通販の虎」をきっかけに「にっぽんの宝物」に参加してくれた事業者さんがいました。彼らの多くは、非常に能動的かつ前のめりな熱量を持っていた。それは、これまでの参加者とはまた違う特性でした。
僕たちのセミナーには、スマホなどデジタルデバイスに慣れていないご高齢の事業主さんも多く参加します。こうした方々が時代に取り残されないようにサポートすることも、これまでの活動で大切にしてきました。
一方で、今回のようにオンラインに精通する事業者さんが参加することで、新しい化学反応が得られるとも考えました。それは都内でユニークな活動をしている人かもしれないし、自分の住む地域では学ぶ機会を得られにくい、離島で活動する人かもしれません。
オンラインサロンであれば、後者のように離れた場所で活動する人々にも、「にっぽんの宝物」のプログラムを届けられると考えました。
――オンラインサロンでは、具体的にどのようなことが体験できるのでしょうか?
大きく分けて三つの体験と価値を提供します。
一つ目は、僕の講義と商品の個別指導をセットにしたセミナーです。僕の講義では、全国を回って掴んだ「売れている商品の特徴」を、最新の市場トレンドやデータをもとにお伝えします。そして個別指導では、自分の商品をみんなの前で発表してもらい、僕だけでなく、他の参加者も含めて全員で壁打ちをします。
この「全員で壁打ち」というのが非常に重要です。たいていの事業者は、自分の商品のことは思い入れが強くて、どうしても客観的に見られなくなります。でも、他人の商品を消費者目線で「これ、欲しいかな?」と見ると、結構シビアな意見が出てくるものです。
背景を何も知らない状態で、わざわざお金を出して買いたいと思わせるにはどうすればいいか。他者の商品へのフィードバックを繰り返すことで、自分の商品の強みや弱みが浮き彫りになっていくんです。

――インプットとアウトプットの両方ができるわけですね。
二つ目は「全国会」です。これはオンラインサロンの会員だけでなく、今年「にっぽんの宝物」に参加している青森、奈良、岩手など、全国10地域ほどの事業者さんが一堂に会する交流会です。
全国会には、毎回スーパーゲストをお呼びします。例えば、昨年度の日本一チャンピオンが登壇し、「どうやって日本一になったのか」「グランプリで売上はどう変わったのか」といったリアルな話をしてもらいます。
10月のセミナーでは、ドバイで客単価10万円の高級レストランを経営する日本人オーナーが登壇します。「今、富裕層には何が受けているのか」「こんな食材を持ってきてくれたら、うちの店で絶対に使いますよ」など、ネットでは聞けないリアルな事情を話していただく予定です。その後も、大手広告代理店・博報堂の広告クリエイターさんなど、さまざまなゲストが登壇します。
――普段は出会えない人から、商売のリアルを聞けるのですね。
そして三つ目は、「全国の仲間との交流」です。
例えば、自分がスイーツを作っていて「もっと特別な牛乳や小麦を使いたい」と思っても、自分の地域には望む商品がないかもしれない。しかし全国レベルで見渡せば、こだわりの製法で作っている生産者が必ずいます。そういう人と出会うことで、新しいコラボレーションや販路拡大の可能性が生まれるわけです。
セミナーや全国会はライブでの参加ももちろんできますし、後日動画としてオンラインサロンの会員さんに配布します。とはいえ、「にっぽんの宝物」は直接アドバイスをもらえたり質問できたりするライブ参加に大きな価値があるので、ぜひ積極的に参加してほしいですね。
未来のヒットメーカーたちへ。原石とやる気で、世界を変える波に乗れ

――「にっぽんの宝物 オンラインセミナー 2025-2026」には、どんな方に参加してほしいですか?
次の二つを持っている方々には、ぜひ参加してほしいなと思います。
一つは「原石」、つまり商品を持っている方々です。
「自分たちが作っているもの、売っているものは間違いなく良いものだ。でも、思うように売れてないしどうすればいいのかわからない」
そんな悩みを抱えている方々は、オンラインサロンで必ず飛躍のヒントを得られるでしょう。
そしてもう一つが、「素直なやる気」です。
――素直さというと?
「にっぽんの宝物」に参加する方の中には、自分の商品に絶対の自信を持っている人が多いです。それ自体は素晴らしいことですが、その自信ゆえに周りからの意見を聞き入れられないこともあるんです。
「にっぽんの宝物」は個別指導のように、みんなでフィードバックをし合って磨き上げるカルチャーです。例えば食品の場合は、「とても美味しい」「普通に美味しい」「自分には合わない」という三つの評価で全員がジャッジします。
ある時、セミナーに全国的にも有名な銘菓を扱う事業者さんが参加しました。しかし個別指導では、大半の参加者が「自分には合わない」と評価したんです。僕自身もこの意見でした。周りの反応を見てショックを受けた事業者さんは、残念ながらそれ以降のセミナーに参加しませんでした。
逆に、すでに大きな成功を収めている企業でも、周りの意見を参考にしてさらに飛躍した事例があります。高知の「ミレービスケット」というお菓子をご存知ですか?全国的にも有名なお菓子ですが、メーカーの副社長さんは毎回セミナーの最前列に座り、熱心に話を聞いてくださっていました。
すでに多くのファンがいるこの商品に対して、僕は磨き上げの一環として他の事業者さんとコラボしたらどうかと提案しました。そして、「にっぽんの宝物」に参加していた若いカフェ経営者とコラボした新商品を開発し、それが大ヒットしたんです。
――すでに大成功を収めている商品でも、意見を聞き入れる姿勢がその後の飛躍を左右したのですね。
人の意見に耳を傾けるのが難しい方には、正直、「にっぽんの宝物」は地獄のような場所かもしれません(笑)。僕たちは本気で目の前の商品を磨き上げたいので、作り手にとって厳しい現実を突きつけることもあります。しかし、そのフィードバックを謙虚に受け止められれば、ここでのやりとりは最高のマーケティング調査になるはずです。
僕らは今、そのための新しい仕掛けを国内外で準備しています。このオンラインサロンが、皆さんと一緒にその新しい波に乗り、世界的なヒットを生み出すための場所になれば嬉しいです。あなたの商品が、全く新しい価値となって世界に羽ばたいていく。そんな可能性を、ぜひここで掴んでほしいと思っています。
「にっぽんの宝物 オンラインセミナー 2025-2026」では今後、魅力的なゲストを招いてのセミナーや商品の磨き上げを目的としたさまざまなプログラムが開催されます。自分の持っている商品を全国、そして世界に愛される宝物にしたいという人は、ぜひ参加してみてください!